ー はじめに ー
一般に芸術作品については、その作者が何らかの意図をもって制作し、それを作品の鑑賞者が理解しようとする、という構図が想定される。もちろんここに関わる三つの審級(作者・作品・鑑賞者)については、その間の関係に多種多様なあり方がありえるだろう。極端な考え方としてすぐ思い浮かぶのは、例えばジョン・ケージの考え方で、彼は、この三つの間には何の関係もない、と言い切っている(1961年刊の『サイレンス』)。しかし、逆の見方からすれば、これは三者の間に「何の関係もない」という関係がある、ということだとも言える。いずれにせよ、ケージでさえこの三審級の存在は認めているのである。彼の主張は、ただこれらの間の何らの位階制も認めないということだと考えられるだろう。
しかし、われわれは普通、作品を前にして、これがどのようなことを言おうとしているのかを考える。そしてその作品の作者について語られるとすれば、その作者が何を言っているのか、言おうとしているのか、即ちどのような意図をもってこの作品を作ったのか、を考えるのだ。もちろん、そのようなことは何も考えずに、ただ単に作品を享受するだけの態度もありえるだろう。しかし、ひとたび作品を解釈しようという態度になると、作者の意図について考えざるをえない。
文学の場合
このような問題については、音楽の分野よりも文学の分野でより進んだ研究がなされている。それは音響よりも言語の方が(一見すると)はっきりした意味をもっているからであろう。いま、まず音楽作品について考える前に、文学作品についての解釈と意図の問題について、どのような議論がなされているのかを見ておくのも無駄なことではないと思われる。
伝統的な文学批評では常に作者の意図について語られてきた。20世紀後半になって、そのような伝統批評について異議を唱えたのが、構造主義やニュークリティシズムと言われるような動きである。この立場は1967年に「作者の死」を書いたロラン・バルトに代表される。作品の解釈において、まず第一に作者の意図を探ろうとするのは正しい解釈とは言えない、とされる。作品の解釈については、例えばそこに何を読み取るかという読者の立場というものも関わってくる。それは歴史的にも変遷するようなものだ(ヤウス「期待の地平」1970)。また作者でさえ意図していなかったような作品が生み出されることもありえる。テクストが自己生成していくようなこの運動を明らかにしたのがジュリア・クリステヴァである(「間テクスト性」1966)。
これらの「反意図主義」への反動として、例えばE・D・ハーシュなどが、文学的言説のあり方が基本的に日常的な発話としての言説と同類であるとみなして、作者には必ず伝えるべき意図があり、それがなければ作品など書くはずがないとして「現実的意図主義」を唱えた。またJ・ロビンソンなどは、ハーシュのそのような「強い意図主義」に対して、やはり芸術と日常会話は同列に論じることはできないとして、より現実的な反論としての「仮想的意図主義」を唱える。これは、テクストから想定される「内包された作者」を設定して(これは現実の作者とは違う)、そのテクストが対象として狙っている「意図された読者」に対してその「内包された作者」が「仮想的意図」をもってテクストを「書いている」という主張をするのである。
いずれにせよ、それぞれの論者にとっては、その論旨にうまく当てはまるような文学作品があるわけで、その「読み」の多様さが、そのどれが「正しいのか」という議論は別にして、もともと文学作品の持っている豊かさの証であるだろうという印象を受ける。バルトに読まれるバルザックや、ロビンソンに読まれるトーマス・マンは、まさにそれぞれの読みによって、わたしたちの知らなかった芸術性が明らかにされているのである。
音楽の場合
さて、翻って音楽作品については、どのように考えるべきであろうか。ここには文学作品よりもはるかに難しい問題があるように思える。それはまず、作品の意味の問題であり、それぞれの音楽作品は何を意味しているのか、ということである。
音楽作品の意味については、文学とは違って、もともと意味をもっている言葉のようなものではない音響を素材とするために、むしろ多く議論をされてきたとも言えるだろう。(アフリカのトーキングドラムなどは言語的意味を担うことができるが、例外的存在と考えられる。)
わたしたちは、ふだん漠然と、音楽は作曲家がある種の意図や伝えたいものごとがあって、それに基づいて作曲されて、それらが演奏によって伝達されて聴衆のもとに届くと考えている。例えば、ベートーヴェンは《第九交響曲》によって、苦難に満ちた自らの人生を振り返って、「困難を通って歓喜へ」というメッセージを伝えようとしたのだ、と思ったりする。これは、ベートーヴェン自身が「音楽はその魂から炎を打ち出さなければならない」などと手紙に書き残しているところから、後世の人間がさまざまに彼の音楽を
それと異なり、同じベートーヴェンの晩年の作品でも《弦楽四重奏曲第15番》作品132の第3楽章には、作曲者自身の手によって「病から癒えた者による神への感謝の歌」と書かれていて、その意図も意味もはっきりしている。重病から回復したベートーヴェンが神への感謝の音楽を書いたのである。しかし、ここで意味や意図がはっきりしているのは、ベートーヴェンがその原稿に言葉によってその意味・意図を書いてくれていたおかげであり、それがなければやはりわたしたちにとって、その意味・意図は不明なままであっただろう。
音楽作品の無意味性
このように、どうしても、それ自体が(原則として)無意味な音響を素材としている音楽は、言葉による説明、言語による補助がなければ、その意味も意図も明らかにならない。それが何を言っているのかわからない。「ソナタよ、わたしにどうしろというのだ」という問いは、フランス啓蒙期の思想家、フェヌロンが発し、それをルソーが自らの『音楽辞典』の中に引用しているので有名だが、同時代のクープランのように「修道女モニク」とか「ティクティクショク」とか「百合の花が開く」とか、その音楽についての説明になるようなタイトルがない場合 — それはまさしく「ソナタ」や「交響曲」といった場合だが — 、そこには意味・意図について考える手がかりが全くないのである。
このような音楽の無意味性について、カントは『判断力批判』の中で、それを音楽という芸術ジャンルの価値が低いことの理由としている。何を言いたいのかわからない以上、それは単に心地よい遊びにすぎない。真剣に取り合う価値のないものである、と言うのだ。しかし、この無意味性が、後の世代のドイツ・ロマン主義の思想家たちにとっては、カントとは真逆に、芸術としての価値の高さの理由となるのである。それは、彼らが芸術に対して、理想の存在を求め、それゆえ現実世界からいかに遠く離反できているか、を芸術評価についての価値基準としたからである。その論理からいえば、絵画や彫刻(当時は抽象芸術がなかった)は直接的に現実を写すことを目的とするために、現実と全く離れることができていない。文学も然りで、小説は現実世界を写しているし、詩の方はやや現実から離れているとはいえ、その表現媒体である言語は日常的に一般人が使っているものに過ぎない。それらに比べて音楽は、まず第一に素材がピアノやヴァイオリンなどの音という、現実には存在しないものであり(当時は騒音や環境音による音楽はない)、それらから生み出される音楽作品は、これまた現実のものは何ものも表現してはいない。まさに純粋芸術の極地が音楽なのである。
現代における音楽美学の見方
このような考え方を基本としているのが、18世紀半ばに生み出され、19世紀(20世紀も大部分)を通じて発展してきた音楽美学である。そこには音楽芸術作品の価値判断の基準として、純粋性・絶対性・自律性という重要な三つの契機がある。それはひとことで言えば、「オペラや歌曲などのように言葉を混ぜることなく、音響だけでできているか(純粋性)」、「ワルツ(踊るため)や歌謡曲(人気を得るため、売るため)のような機能性をもたないでいるか(絶対性)」、「それ自体が入念に練り上げられ、音楽分析という処置に耐えることができるか(自律性)」ということである。その最高のモデルはベートーヴェンを頂点とする古典派のソナタや弦楽四重奏曲、交響曲であった。
しかし、このような考え方が、近代ヨーロッパという時間的にも地理的にも非常に狭い時代・地域でのみ有効な、非常に特殊なものであることはまた明らかである。ジャワのガムランも日本の雅楽も、はっきりした機能をもった宮廷音楽であるが、いずれも素晴らしい音楽であることに変わりはない。北インドの古典音楽は、音楽分析には適しない、元来が即興をもとにした音楽であるが、やはり素晴らしい。同様に、同じヨーロッパでも、音楽美学の生まれる前の時代のバッハの音楽は、声を使った不純なものだし、教会の行事のために書かれた機能性をはっきりもっているが、その価値を疑うものはいないだろう。
こうした近代的音楽美学思想の矛盾点を暴くような音楽作品が生み出されるようになってきたのは、20世紀に入ってからである。まず、雑音や騒音、日常音などを音楽の素材として使うようになってきた(ルッソロ「騒音芸術」[1913]、ヴァレーズ《イオニザシオン》[1931]、ケージ《4分33秒》[1952])。またクラシック音楽とポピュラー音楽との間の垣根も低くなる、あるいは取り払われていった(クルト・ヴァイル、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト、ジョージ・ガーシュインなど)。音楽分析など不可能な即興、一音の音楽(ラ・モンテ・ヤング)、無音の音楽(ケージ)は言うまでもない。もはや、純粋・絶対・自律の近代的音楽美学は過去のものとなった感がある。
現代音楽作品の意味・意図
さてしかし、そのような現代の動向において、音楽作品の意味や意図についてはどう考えたらよいのだろうか。
近代的音楽美学においては、音楽作品は純粋・絶対・自律的な
このようなブーレーズの考え方は、当時の文学を含めた現代芸術の一般的動向と関連がある。先ほど述べたロラン・バルトなどの構造主義者たちが主張していた「作者の死」という概念や、テクストの「自己生成」などという概念がここに反映していることは明らかだ。ブーレーズは敏感に当時の世相に反応していたのである。ただ、音楽芸術の分野においては、それが音楽美学的に見れば18、19世紀的な時代遅れなものと見えるパラドックスがある。(これは「音楽からその富を奪」って、新しい詩を生み出そうとしていた、ステファヌ・マラルメを中間項として考えると、うまく理解できるだろう。)
ここで、もっと広い視野でのアクチュアリティを常に持ち続けていた作曲家であるリュック・フェラーリの作品を取り上げ、考察することによって、現代の音楽作品における意味・意図の問題を詳しく明らかにすることができるのではないだろうか。フェラーリの《チェンバロとテープのための共同プログラム》(1972)は、同時期にフランス政治界で起こった一事件、共産党と社会党が団結し、合同して共闘のためのプログラム(共同プログラム)を発表したこと、と関連がありそうにみえる。しかし、はたして、はっきりとそう言えるのだろうか。言えるとしたらその理由は何か、また言えないとしても、またその理由は何だろうか。
ー フェラーリ《チェンバロとテープのための共同プログラム》について ー
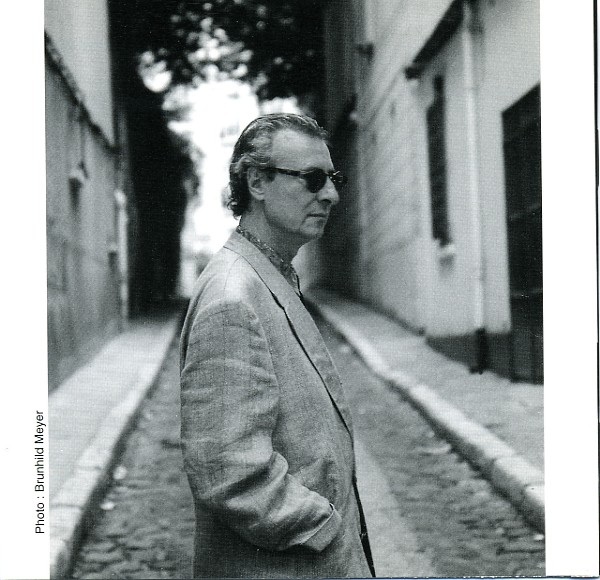
Luc Ferrari ( 1929-2005 ) パリ5区の自宅近辺にて。
わたしたちは、この作品を理解するためにどうしなければならないのか。作品理解の手がかりには何があるのだろうか。わたしたちにはさまざまな手がかりが残されている。まずは、タイトルそのもの。そして楽譜。また作品に直接関わるものとして、楽譜に付された作曲家自らの言葉がある。そして自作の作品カタログに残された作曲家の言葉もある。さらに、この作品は初演以来、何回か演奏されたり録音されたりしているが、そのたびにやはり作曲者によって解説が書かれている。
またこの作品が書かれた当時の政治・社会的状況についても深い知識が必要なのは言うまでもない。それについては、またさまざまな手段で情報を集めることが可能だ。
さらに、当時の文化的・芸術的・音楽的なコンテクストを理解しておくことも重要だろう。そんな中での作曲者本人の音楽活動・作曲活動の状況(その歴史・軌跡やその背後にある思想や哲学)について把握しておくことも作品理解には大切だろう。
作曲者の言葉
まず作曲者本人の言葉を引く。これらは作品のカタログや録音そのものに付されている言葉であり、公式なものと考えられる。まずは1977年にERATOから発売された、エリザベート・ホイナツカの演奏によるLPレコード(STU 71010)のライナーノートの文章で、以下のようなものである。
社会主義音楽?
あるいはチェンバロとテープのための共同プログラム
(1972年1月〜10月)
なぜこのタイトルなのか?
[この作品の]聴取以前、あるいは聴取後に、この問いは問われたままだろう。あるいは再び問われるだろう(これにより疑問符が付されるのだ)。それは、総選挙の以前あるいは以後に、〈社会主義〉の大いなる問題が問われたままであるのと同様である。
(比較はしたくはないけれども、現代社会の外側で人は生きることができるだろうか?[いや、できない。])
反動家たちが、彼らの言うことを喜んで聞く素朴な人々を前に、外国に存在する社会主義体制を断罪すること、それはもっとも有利でもっとも簡単な解決法である。もっと難しいのは、不当な利益に基づかないような独自な社会を建設することである。そしてこれ、これはすべての人に関係している、芸術家たちにさえも関係しているのだ。
(私は政治をするのではなく、社会の中にその位置を持っているはずの
この探求に参加すること、これが昔から私の唯一の興味であった。
(私の領野では、例えそれが非常に控えめなものであったとしても、行動というものがその場を得ているということは、言っておかなければならないだろう。結局のところ、私はあきらめないのだ。)
どうして、この支配的な関心が私の仕事のうちで表現されてならないということがあるだろうか、そうでしょう? 否が応でも社会的希望と芸術的希望は切り離すことはできない。[しかし]旧来の特権を保護するために人はしばしばそうしようとするのだが。
それが映画の中に見られるような直接的なものであろうと、私の音楽の中でのような間接的なものであろうと、問いは問われたままなのである。すなわち、
(ここにそれを再び問う。問いは二重になっている。発言権を握っている間になるべく話しておこうじゃないか。)
— 特に、私のタイトルと私の作品の間に関係はあるのだろうか?
— 一般に、どのようにして芸術活動において新社会建設にむかって仕事をすることができるのだろうか?
(これこそが問いである。私にはわからない、しかし答えを探している、探し続けているのだ……。)
スタジオ・ビリッヒにて製作
GMEBのスタジオで最終ミキシング
この文章は、現在手に入れることができるこの作品の楽譜の最初にも記されており、一言一句全く同じものである。その日付は作曲年と同じ1972年である。(1)
そして、その次は自身で作成した作品カタログ「混乱した軌跡」(2) 内の記述である。
《チェンバロとテープのための共同プログラム》(1972)— 約20分。
増幅されたチェンバロと磁気テープのための。
初演、パリ、エリザベート・ホイナツカによる。GRMコンサート、レカミエ劇場にて、1973年。
これは楽しい音楽である。しかし、ひとつの問いを問うている。すなわち、政治的関心と芸術的関心のふたつを、(映画の中でするように)直接的にでも、あるいはこの曲の中でのように間接的にでも、ふたつを切り離すことができるのだろうか? だが[この作品は]特に、私のやり方によって、1972年の「共同プログラム」調印を記念するものなのである。
これらの言葉からわかることは、この作品が当時の「現代社会」の状況と密接な関連があるということである。彼が述べている「総選挙」、あるいは「共同プログラム調印」というのは何なのであろうか。次にそれについて調べてみよう。
注
(1)1973年パリでの初演後、この作品はロワイヤンでも演奏の予定があったらしい。そのときに書かれた解説は全く違ったもので、わたしたちはそれをブリュンヒルド・フェラーリ夫人のご好意で手に入れることができた。本稿の末尾にそれを訳出しておきたい。
(2)この作品カタログは、表紙裏に「これは作品カタログではない」と記され、続いて「私の全作品、全演奏が記載されている軌跡」であるとされるが、随時更新されており、フェラーリ没後は夫人によって更新され続けている。筆者の所有する最古の版は1999年頃のものだ。
「政府共同綱領Programme commun de gouvernement」について
ここで問題となるのは、第二次世界大戦後のフランス政治の歴史であり、その中での左翼勢力の動きである。特にフランス共産党は、戦時中のレジスタンス運動などの影響で、戦後間もなくの選挙では大勝し、第一党となったりもしているのだが、さまざまな政治の動きから取り残され、1958年からの第五共和制のもとでは、ドゴール大統領の保守勢力の伸びによって、弱体化していっていた。そのような中で1965年の大統領選挙のときに、フランス共産党は既にドゴールの対抗馬としてのミッテランを支持し、社共の共同体制への道を歩み始めていたと言われている。
その後、1968年の五月革命によってドゴールの政治生命は絶たれ(生物学的生命も1970年11月には終わってしまった)、次の大統領はドゴール時代の首相だったポンピドゥーになった。そんな政情のなか、ミッテランを中心に旧社会党(SFIO)の再編が行われて「新生社会党」(PS)が生まれる。というのも、1969年の大統領選で社会党は、共産党候補の得票の4分の1にも達せず、根本的な体質改善が望まれていたのである。ミッテランは、強大な与党の前には左翼勢力の結集しか勝利への道はないと確信していた。
そのような政治状況の中、1973年総選挙を戦うにあたって、社会党と共産党は急接近し「政府共同綱領Le programme commun de gouvernement」を作り上げるのである。通称「共同綱領Le programme commun」と呼ばれるこの政治プログラムの中身は、「既存体制の不正と不整合に終止符を打ち」フランス国民全員に「よりよく生き、生活を変える」というスローガンのもとで、さまざまな改革案を提示している。その内容を要領よくまとめている文章があるので、引用しよう。
この共同綱領は、「真の政治的・経済的民主主義を樹立する」ことを目的として、四部構成をとっている。第一部は労働者・一般庶民の日常的・経済的条件の改善を内容とする。第二部は、「経済の民主化、公共部門の発展、進歩の計画化」を掲げ、重要部門の国有化・民主化、そして企業における労働者参加と民主的管理が強調された。しかし、この部分では、「労働者の自主管理」を企業民主主義の中心とする社会党と「人民政府の革命的集権主義」を主張する共産党との間には見解の開きがあったし、さらに国有化の範囲においても両党間の見解には乖離があった。第三部では大統領権限の縮小、多党制、比例代表制導入などを含む政治制度の民主化が提唱され、第四部では対外政策が扱われていた。とくに、欧州安保とEC問題では、北大西洋条約機構とワルシャワ条約機構の同時解体と、ECへの参加を主張する社会党とそれに反対する共産党の立場は異なっていた。(渡邊啓貴による論考)
ここで最後に指摘されている社会党と共産党の不協和音の他にも、この綱領には基本的な財源について曖昧なままになっている欠点が夙に指摘されており、多くの問題を最初から孕んでいたが、何はともあれ、1973年総選挙では社会党得票数の増大(20%増)と、1974年大統領選での左翼連合統一候補(ミッテラン)選出へと道を開くことになった。
1977年に、勢力弱体化を危惧した共産党が社会党に対して、綱領の具体的な現実化路線を迫り、かつ企業内での組合の力を増大させるなどのより現実的左翼的な施策を要求するのだが、これを社会党が拒絶し、事実上「共同綱領」は無効となってしまった。しかし、ここに始まった左翼連合の動きは、政界の大きな再編の動きへと繋がり、最終的には1981年大統領選でのミッテラン勝利にまでフランスを導くことになったのである。
政治と音楽の関係
以上のことからわたしたちは、フェラーリの語る「総選挙」が、1973年の総選挙のことであり、「共同プログラム調印」というのが、社会党と共産党の間で交わされた「政府共同綱領」の調印のことだということがわかった。「総選挙」の前後に「社会主義の大いなる問題が問われた」というのは、この綱領の中で語られている政治主張が本当の社会主義なのだろうか、これによって本当に社会が改善され、人々がより幸福になるのだろうか、というような問題が問われたことと推察されよう。そして、より現実的な見方をすれば、はっきり言ってこの綱領は共産党と社会党が総選挙で勝利するための協定であり、それが証拠にこれらのバラ色の諸政策を実現するための現実的基盤である経済政策については、言わば、ないがしろにされているのだ、と言うこともできる。こうした「政治屋主義」の裏工作的側面をフェラーリが、この「政府共同綱領」調印の、人目を引くパフォーマンスに嗅ぎ取ったということもありえることだ。それゆえ、彼はタイトルの「社会主義」の語に疑問符を打ったのではないだろうか。
そしてまた同時期にフェラーリが二本のドキュメンタリー映画『ほとんど何もない あるいは生きる欲望Presque rien ou le désir de vivre』を撮っていることも、当時の彼の関心がどこにあったかを推し量る材料となる。この映画は「第1部:コース・メジャンLe Causse Méjean」「第2部:ラルザック高原Le Plateau du Larzac」となっており、前者は南仏の寒村で暮らす人々、荒れた土地で細々と農耕・牧畜で生計を立てている人々に寄り添い、いかに都市において文明が進んでいても、そんなものには何の関係もなく厳しい自然と向き合って生きざるをえない人々の過酷な現実を描いているし、後者はやはり南仏のラルザック高原に降って湧いた陸軍演習場拡張計画と、土地住民の意向を無視した政府の強引なやり方に対して立ち上がった、無力な小農民・牧畜民たちの無謀ともいえる戦いを描いている。このような映画を撮影する中で — あるいは撮影しようと思った段階ですでに — 、フェラーリが社会の不正や不公平に敏感に反応しているのが見て取れる。
このような背景から彼の「不当な利益に基づかないような独自な社会を建設すること」という言葉の意味がよくわかるし、そのために彼が芸術家として何ができるのかと問うているのも当然のことだと思われる。作品カタログ「混乱した軌跡」の中には、同時期に同じような関心からフェラーリが創作したであろう作品として、例えば「プレイライトとタイムショー」と名付けられている《もしもし、こちら地上》(地球上の環境破壊を糾弾する内容の、演出を伴った音楽とスライドショーで1971〜72年の作品)や、《アルジェリア76》と題されたテープとスライドのための作品(フランスからの独立後の社会主義政策の中で苦労しながら生活するアルジェリア農民を描くもので1976〜77年)、《トゥシャン、村11350番》(南仏の寒村トゥシャンでの貧しい農民たちの暮らし。音楽・インタビュー・スライド、1976〜77年)、《シャンタル》(同村に暮らす若い女性シャンタルのインタビュー。1977〜78年)などがある。
《チェンバロとテープのための共同プログラム》における政治と音楽
さて、こうして彼が「芸術家として」できることとして為したことが、上述のような作品群と並んで《チェンバロとテープのための共同プログラム》作曲であったのだろうか。はたしてそのように単純に言えるのであろうか。
ここでフェラーリ自身の言葉に再び戻ってみよう。彼はこう言っていた。「どうして、この支配的な関心が私の仕事のうちで表現されてならないということがあるだろうか」と。つまり、彼のもつ社会的・政治的関心が彼の「仕事」すなわち音楽の中で表現されるという可能性について述べているのだ。すると、この「不正な利益に基づかないような独自な社会を建設する」という関心は彼のこの作品の中で表現されているのだろうか。
それを肯定するかのように言葉は続く。「否が応でも社会的希望と芸術的希望は切り離すことはできない。[しかし]旧来の特権を保護するために人はしばしばそうしようとするのだが」。「旧来の特権を保護する」とは、おそらく以前に述べたような西洋近代的音楽美学に基づいて、芸術音楽を社会や政治から無関係な「特権的な」
ところが、彼の文章は予想外の方向へとわたしたちを導いていく。直後に彼はこう続ける。「それが映画の中に見られるような直接的なものであろうと、私の音楽の中でのように間接的なものであろうと、問いは問われたままなのである」。ここで述べられている「映画」というのが上述の『ほとんど何もない、あるいは生きる欲望』二部作であることは、ほぼ間違いないだろう。確かにここでは「直接的に」社会や政治の不正が糾弾されていた。それでは音楽作品においては「間接的に」社会や政治の不正が糾弾されているのだろうか。いやいや、わたしたちは先走りすぎている。この文章では「映画の中に見られるような直接的なものであろうと、私の音楽の中での間接的なものであろうと」為されている行為とは、不正の糾弾や不公平の弾劾などではないのだ。そうではなくて、それは「問い」を「問うこと」である。
フェラーリの第一の問い
それではその問いとは何か。すぐに彼は言葉を継ぐ。「ここにそれを再び問う。問いは二重になっている」。その「問い」は「二重になっている」のだ。ではそれは具体的には何かというと、以下の二つの問いである。
— 特に、私のタイトルと私の作品の間に関係はあるのだろうか?
— 一般に、どのようにして芸術活動において新社会建設にむかって仕事をすることができるのだろうか?
このように特殊な問いと一般的な問いを二重にするところは、まさにフランス的な哲学的ディセルタシオンの正統派的物言いである。作品のタイトルと作品自体との関係という「特殊問題」と、芸術活動の中で政治・社会的な活動がどのように可能なのかという「一般問題」の二つが提示されているのだ。この「二重の問い」が、『ほとんど何もない、あるいは生きる欲望』と《チェンバロとテープのための共同プログラム》では、前者では「直接的に」後者では「間接的に」問われているのである。一つ一つ見ていくことが必要だろう。
まず第一の問い、すなわち「私のタイトルと私の作品の間に関係はあるのだろうか?」である。映画の『ほとんど何もない、あるいは生きる欲望』では、フランス僻地の寒村で過酷な自然や不正で暴虐な政治権力と戦いながら懸命に生きる小農民たちが描かれていた。「生きる欲望」とは、そのような彼らが懸命に生きていこうとする原動力を表現しているという意味で、非常にわかりやすいタイトルとなっている。彼らは過酷な自然や暴虐な政治権力を前にして、簡単に降参して死んでしまうのではなく、少しでも「生きて」いきたいのである。では「ほとんど何もない」とは?
「ほとんど何もない」とは、映画の2年前に発表された、リュック・フェラーリの代表作《ほとんど何もない、あるいは海岸の夜明け》のタイトルでもある。このテープ作品が「ほとんど何もない」のはなぜかといえば、クロアチアの或る漁村における夜明けの情景がただ単にそのまま録音されて聞こえてくるからだ。そこには、犬、子ども、女性たち、トラック、鶏、ボート、セミなどの物音のほかには何もない。そしてまた作曲者の操作も「ほとんど何もない」。実際には、録音された素材は非常に巧妙に操作され、編集されているのだが、それが「ほとんど何もない」ように聞こえる。それでは、この音楽作品と映画との間にどのような関連があるのか。
まずは現場が一方は人里離れた漁村であり、他方は僻地の農村だということがあるだろう。そのような場所で暮らす人々、大地に根付いた人々の生活が素材だという共通点がある。そして実際にどちらの寒村にも「ほとんど何もない」のだろう。文明の利器といえば、トラックとかラジオとか、そのようなものしかない。あとは先祖代々営々と気づいてきた素朴な生活があるだけだ。
またフェラーリがそのような素材を扱う手つきも、映画においても「ほとんど何もない」ように見える。一見すると、ドイツから来たレポーターがいろいろな取材を実際に行っているかのようだが、実際にはそのようなレポーターは存在しないし、だからこれが本当のドキュメンタリーなのか、巧妙に作られたドラマなのかは実のところ曖昧なままである。音楽作品と映画作品との両方を知るものにとっては、このタイトルはさまざまな多義性を孕んだ、実に巧妙な
次に《チェンバロとテープのための共同プログラム》だが、ここではもちろんフェラーリ自身が言及する、社会党と共産党の「政府共同
しかしわたしたちは、この音楽作品の中で「共同」して、同じ「プログラム」を実行している要素にすぐに気づく。それはチェンバロとテープである。こうして、1972年当時のフランス政局の動きを全く知らない聴衆も、「共同する」チェンバロとテープの作品であるこの作品を「共同プログラム」というタイトルのもとに理解することは容易である。それゆえフェラーリはタイトル全文の中に「チェンバロとテープ
では「共同綱領」は? これもまたフェラーリ流の
フェラーリの第二の問い
第二の問いは「どのようにして芸術活動において新社会建設にむかって仕事をすることができるのだろうか」というものだった。これは「一般的な問い」であった。すなわち、第一の問いが「特殊な」ものであり、映画『ほとんど何もない』や音楽作品《チェンバロとテープのための共同プログラム》という個々の作品に関わるものだったとしたら、この第二の問いはもっと「一般的」にすべての芸術家たち、すべての芸術活動に関わってくるようなものだということだ。そしてこの問いについても、映画においては「直接的」に、音楽においては「間接的」に、問われているのだ。順番に見ていこう。
まず映画作品においては、過酷な自然や暴虐な政府の施策に喘ぐ小農民たちの現実が描かれることによって、それらの不正や不条理をわたしたち観客に「直接的」に知らしめている、ということが言える。このことによって、少しでも「不当な利益に基づかないような独自な社会を建設すること」に向かって、人々の意識を高めることができるのではないかと希望することはできる。もちろんそれがすぐに効力を発揮するとか、本当にその方向への努力と直結するというのは、正直なところ未知数であることも確かである。しかし、とりあえず現状でできる範囲での「芸術活動における新社会建設にむかう仕事」のあり方として考えられるものだということは少なくとも言えるだろう。
では音楽作品ではどうだろうか。これはもっと曖昧である。先ほども述べたように《チェンバロとテープのための共同プログラム》が、社会党と共産党の間で調印された「共同綱領」に対しての
しかしまた、これが1981年の社会党政権成立への布石となったことも確かである。そして、この社会党政権成立のおかげ(文化省音楽舞踊局長モーリス・フルーレの慫慂)で、フェラーリは「回路の詩神La Muse en Circuit」協会を設立することができるようになったのである。もちろんこれは過去を見通す現在のわたしたちの視点からの、いわばアナクロニックな見方なのであり、1972年の時点でフェラーリがそこまで予測できていたかどうかは、むしろ否定的に考えるべきだろう。しかし彼自身が言うように「社会の中にその位置をもっている
いずれにせよ、以上の二つの問いについてフェラーリは最後にこう付け加えている。「これこそが問いである。私にはわからない、しかし答えを探している、探し続けているのだ……。」結局のところ、彼自身にも答えはわからないのである。こうして、特殊な問いと一般的な問いの二つの問いは、映画において直接的に、音楽において間接的に問われ、それらが上演・演奏されるたびに、問われ続けていく。
《チェンバロとテープのための共同プログラム》の解釈の可能性
わたしたちはこうして、ひとまず結論として、この《チェンバロとテープのための共同プログラム》においてタイトルと音楽に関係があるのかどうかわからないし、この音楽においてどのように新社会建設への仕事が成し遂げられているのかもわからないし、作曲者自身がこの問いを問い続けているのだということがわかった。しかし、いわばこれは
近藤譲は、彼が2005年に書いたアコーディオンと弦楽四重奏のための作品に《ヤーロウ》(セイヨウノコギリソウ)と名付けたのは「この作品の最初の音を書くためにピアノに向かった時、妻がハーブガーデンから摘んで来たヤーロウの強い香りに包まれていた」からだと述べている。このようなタイトルの付け方はつまりはタイトルと音響のあいだには直接的な関係は全くないと言っているわけで、聴衆がタイトルのセイヨウノコギリソウを知っている必要さえないのである。単なる符牒といってもよい。「作品1」「作品2」と呼ぶかわりに、たまたまそばにあったものの名前をつけたというに過ぎない。(ただし、聴衆は必然的にその名前のものを思い浮かべるし — セイヨウノコギリソウを知っていた場合 — 、そうでなくても何らかのイメージを必然的にもってしまう。そこに近藤譲のある種の思い — 意図? — がないとはいえないだろう。)
さて、また一時期フェラーリとGRMでともに働いていた作曲家のフランソワ=ベルナール・マーシュは、作品とタイトルの関係についてこう述べている。
[前略]一般的に、私は、音楽の聴取にとって有用な方向に聴衆の想像力を導いていくように努力しています。そしてその意味でタイトルの重要性というものを重視しています。私は自作のタイトルを「ア・プリオリに」見つけることはないのですが、作曲し終わるといつも聴衆の立場に立ってみようとします。私が想像した音響の流れについて人は何を聴くだろうか、それを示唆するのにどのような想像界を使ったらいいだろうか。だから私は聴取を誘導するためにタイトルを選びます。でもその誘導は非常に一般的なものなので、聴衆はさまざまな方角に行くことができるのです。私は詩的な表現のタイトル、例えば[ギリシャの詩人]セフェリスから借りた「沈黙の皮膚」のようなタイトルをつけることもあれば、自分で考案した「忘却の祭儀」や「時間の三角江」のようなものもあります。三楽章の協奏曲とか交響曲のように抽象的なやり方ではなく、これらの作品をもっと具体的に聴いて欲しいと思っているのです。(フランソワ=ベルナール・マーシュ、ブリュノー・セルーによるインタビュー)
マーシュは近藤よりも、聴衆のイマジネーションを導くという意図について、はっきりと述べている。しかしそれは「さまざまな方角に」行くもので、多義的であり一義的ではない。
フェラーリの《チェンバロとテープのための共同プログラム》について言えば、タイトルと音楽の関係について作曲者自身が「わからない」「問い続けている」というが、その場合は極端に言えば、近藤譲《ヤーロウ》と同様に、タイトルと音楽は何の関係もない、と言うこともできるだろう。あるかもしれないがわからないのである。
しかしここには「わからない」と言いながら、それによって聴衆の側からの解釈への多義性を増そうという意図もあるのではないだろうか。もしもタイトルと音楽の間には関係があるとなると、それも当時のフランス政局に詳しい人間にとっては(そしてそれは初演時の大多数の聴衆だったろう)社会党と共産党の「政府共同綱領」に由来するタイトルをもつこの音楽がそのタイトルと関係があるとなれば、この音楽は「共同綱領」を賞賛するものと解釈されるかもしれない(この作品が作曲者自身のカタログの記述によれば「楽しいもの」であるだけになおさらである)。少なくともその場合は音楽の意図は一義的に決まってしまう。共産主義万歳、社会主義万歳という音楽である。
この点でマーシュによるタイトルの多義性についての考え方は、同じような文脈に生きる同世代の作曲家として、フェラーリにも共有できるものではなかっただろうか。さらに興味深いことに、マーシュにもフェラーリ作品と同年に書かれ、同じ編成で同じ演奏者によって初演された作品がある。チェンバロとテープのための《コルヴァールKorwar》であり、この作品についてはフェラーリ作品との比較がわたしたちの解釈をさらに深めてくれると思われる。

François Bayle (1932~), Luc Ferrari (1929 ~ 2005), François-Bernard Mâche (1935~ ), Daniel Charles (1935~2008) and François Delalande (1941-)
(左からフランソワ・ベール、リュック・フェラーリ、フランソワ=ベルナール・マーシュ、ダニエル・シャルル、フランソワ・ドラランド)
ー マーシュ《コルヴァール》について ー
この作品については、作曲者自身が初演当時に書いた文章がある。まずそれを引用しよう。
「コルヴァール」というのはニューギニアの部族たちの言葉であり、彼らにとっては精神力の貯蔵庫である頭蓋骨は慎重に保存されるべきものであって、一種の木製家具の中で肉付けされ彩色されて嵌め込まれている。それは、それゆえ、それを覆う粘土と色彩や、それが嵌め込まれた木製土台などを考えると一種の彫刻であり、しかしまた同時に、「美的な」上塗りを通して現れる著しく自然で生なオブジェでもある。
生な音響の録音テープがこのようにさまざまな器楽音楽と結びつけられ、あるいは並置されたりする一連の作品の中で、私は多少ともそれに似たものを作ろうと考えた……。録音されたパートが「生な」音響によってのみ作られていたとしても、その選択と連接については全く自然なものなどないし、ある新しい意味において、そして見た目よりも小さくない量で、私が責任者であるところの作曲行為を構成している。
この方法は、1967年から1969年のあいだ、私がアンサンブル・アルス・ノーヴァの委嘱で《忘却の祭儀》を作曲したときから始まった。しかし《コルヴァール》においては、テープも器楽書法も、それよりはるかに簡素なものとなっている。動物の声の生々しさは意図的に強調されているが、それというのも私には、リアリズムが極端であればあるだけ、幻想的なものに近づくと思われたからだ。しかしそれも条件があって、シキチョウやグアナコやシャチたちなどが音の動物園から外に出て音楽的聴取を促すようになるのに必要な感覚移動に成功するならば、という条件のもとでである。
《忘却の祭儀》と同様に、しかしより辛辣でより抽象的なやり方で、《コルヴァール》は、自然/文化ジレンマへの回答の試みとなっている。チェンバロの役割は、テープ音と対立したり敷衍したりするのではなく、非常に多くの場合それに貼り付いて、重い歴史を担っている楽器として、音楽的身振りと動物の鳴き声そして諸元素の動悸が深いところで一致しているのだということを示すのである。私は現実界に
おそらく《コルヴァール》のような作品が自然と文化のあいだの境界を曖昧なものにすることで成し遂げようとするのは、一つの対抗文化を示唆すること、戯れによって、人間精神が身につけたあらゆる武器(ある者たちによってあまりにナイーブに捨てられてしまった論理も含む)を官制の生真面目さに向けさせることである。中で鳥たちの歌が聞こえるにも関わらず、これは
《コルヴァール》の作品情報も同所に詳しく書かれていて、それによれば、このチェンバロとテープのための作品は、GMEB(ブルージュ電子音響音楽グループ)の委嘱により書かれ、1972年5月にブルージュのGMEBスタジオで完成された。初演は、同年6月30日に被献呈者のエリザベート・ホイナツカのチェンバロで、ブルージュ文化会館にて行われた。
ここでまたひとつ、フェラーリ作品との共通点が明らかになった。それは最終ミキシング、完成形が作られたのが同じGMEBスタジオであることだ。1972年という同じ年に書かれ、楽器編成も同じ、初演の演奏者も同じ、そしてテープ部分の最終形も同じスタジオで作られているのである。もちろんフェラーリとマーシュは、一時期同じGRMで働いていたし、それ以前にはおそらくパリ音楽院のメシアンのクラスでも一緒であっただろうと思われるが、もともとの環境は非常に異なっているし(フェラーリはコルシカを出自とする中流家庭の出身であるのに対して、マーシュはクレルモン=フェラン出身で曽祖父の代から音楽家の家系だ)、音楽的にはかなり相違点の多い作曲家なので、たまたま二つの作品が多くの共通点を持つからといって、それらが同じ関心のもとに書かれたとは、一概には言えないのも確かである。作曲の発端も、マーシュの方はGMEBからの委嘱とはっきりとしているが、フェラーリの方は、夫人からの情報では、ホイナツカからのたっての希望により作曲を始めたという。
フェラーリとマーシュとの関係については、これからより詳細に追っていく必要があるだろうし、この二作品の関係も一筋縄ではいかないものがありそうだが、とりあえずここで言えるのは、1972年当時の政治・社会的雰囲気、4年前に全国を震撼させ、大統領退陣にまで追い込んだ五月革命の余波が続く中での、政界再編の動きなどが、彼ら二人の作曲を同じように包んでいたのではないだろうか、ということだ。
その点に関して、マーシュ自身が、初演から40年後の2012年に、この初演時のテクストについてコメントをしている内容はとても興味深いものがある。彼はこう言う。「このテクストに散見される社会・政治的マニフェストがいかに時代遅れとなっているかを見るとき、それとは逆にこれらは、私には最良のアクチュアリティーを保っているように思える、歴史の特権に対して異議申し立てをしている言葉なのだという思いを禁じえない。1972年において、詩的・革命的ユートピアへの幻滅と、消費という唯一の共同プロジェクトへと大きく口を開けた大通りは、芸術的選択としてはほとんど、屈従あるいはノスタルジーしか可能性がなかったのだった。諸文化の絶えざるカーニヴァルはこの地球規模のスーパーマーケットの表現であった。そこでは、[中略]『経済的恐怖』のコンテクストにおいて、改良発明が一般的に、市場の強制力によって、挑発のアカデミズムと同時にまた、できるだけ急速な退廃化へと運命付けられているのである」(同所)。ここでおそろしく難解な表現によって語られているのは、マーシュのこの作品もまた、今はいかに時代遅れとなろうと、当時の「社会・政治的マニフェスト」としての意味をもっており、その「異議申し立て」の行為は未だに有効であるということだ。そしてまた、1972年当時に、五月革命において幻滅に終わったユートピア構想、それに連れて猛威を振るうようになる高度資本主義社会(消費社会)、それが芸術家たちの態度を萎縮させたという認識だ。その後の「諸文化の絶えざるカーニヴァル」とは、おそらく「ワールドミュージック」などのレッテルで、消費社会に組み入れられ、スーパーマーケットに並べられた諸民族の音楽のことに違いない。そのような経済至上主義においては、芸術上の改良発明などすぐに無効になってしまうという、ペシミスティックな言葉が語られる。
しかし、わたしたちにとっては、こうしてフェラーリ作品とマーシュ作品との両方を包み込んでいる当時の政治・社会的(そして歴史的)文脈が明らかになったといえる。このような懐疑的な状況では、ますます「社会主義」には「?」をつけざるをえないだろうし、「共同プログラム」は「政府共同綱領」そのものでありえないのは火を見るよりも明らかであろう。
ー むすび ー
リュック・フェラーリ《チェンバロとテープのための共同プログラム》をめぐる、わたしたちの旅もそろそろ終着点が見えてきたと言えるだろう。音楽作品の意味とか意図は、現代音楽と呼ばれる時代のものは特に、作曲家自身の言葉だけでは解釈ができない。その背後には、歴史的・社会的・政治的な文脈が存在しており、それらを詳細に検討しなければ、ある程度でさえ、はっきりとした物言いはできないのである。
最後に、ブリュンヒルド・フェラーリ夫人から、本論文を執筆するにあたって、コピーを送っていただいた自筆譜の状態を報告して、この論文を終えたいと思う。そこには表紙の前にタイプ原稿が付されており、そのテクストは以前に紹介した第一のものと同じであるが、タイトルの「社会主義音楽」に「?」が付けられていない。そして、その後は自筆の楽譜が4葉続く。1葉目にはタイトルが書かれているが、それは「チェンバロとテープのための共同プログラム」のみであり、「パリ、1972年1月〜10月」と書かれている。2葉目から最後までは作品本体である。
そして、そのほかに二つのテクストがあり、一つは現在流布している解説のテクストであって、これに見られるタイトルには「社会主義音楽?」と「?」が付いている。もう一つが謎を呼ぶテクストで、「ロワイヤンのために」と題された2ページのテクストである。これについては既に注で言及しておいた。これによれば、どうもロワイヤンで演奏の予定があったようにも思える。そしてまた、マーシュ《コルヴァール》が1973年にロワイヤンで演奏されたことを勘案する(Mâche, Cent opus..., p.95. による)と、同じ機会に演奏された(あるいは予定されていたが演奏されなかった)と考えられるが、いまだ確証はない。(「ロワイヤンのプログラムのために」の言葉が自筆でタイプ原稿に付け加えられている事実がさまざまな憶測を呼ぶ。)
この「ロワイヤン・テクスト」を最後に訳しておこう。一見してわかるように、これは彼の「自伝」シリーズの一部を成すようになるものだ。そしてまた最後に付けられた作品表に現在では確認されていないタイトルがいくつかあることも非常に興味深い。(特に最後の抹消されている「ほとんど何もないあるいは山中の夕陽」とは、演劇の分野に分類されてはいるが、おそらく1973年の映画のことだろうから、《ほとんど何もない、あるいは海岸の夜明け》と映画との強いつながりを主張する、わたしたちの推論の正しさを証明する資料となっている。)
(リュック・フェラーリ、1973年2月19日のノート)
ロワイヤンのプログラムのために[この1行は自筆]
私は、昔の自伝のなか、それぞれの初めの段落のなかに、こんな語句を見出す:
……私は、その名が示すとおり、イタリア系であるが、コルシカを通っている。先祖はそこにやってきた……。
……いつも作曲家は自分についてのテクストを求められる、いつに生まれたか、だれに師事したか、など。パスカードのようなものだ……。
……私は大昔にマルセイユで生まれた……もう覚えていない。私の父もまた自分の誕生日を覚えていない。彼の生まれ故郷の村役場が登記を忘れたか、そのページを無くしてしまったか……。
……私は失敗したイタリア人である、失敗したフランス人である、母からは失敗したマルセイユ人となった、なぜなら私はパリで生まれたから、私は失敗した画家であり、失敗した音楽家であり、失敗した映画監督であり、失敗した作家であり、失敗した幹事であり、失敗した社長であり、などなど……。
……どうして知ることができよう。地球はわたしたちを未完成状態へと巻き込む。それが回っているだけになおさらだ。
……とても暑かった、私は誰にでも「こんにちは、おじさん」といっていた、なぜなら私は……暑さの音が喉に残っていて、それがその沈黙から生まれる歌をあれほど美しくしていた……。
……したことをしたのは間違いだった。私は、過去の人生を振り返るにつけて、いつも間違っていたのだと思う。それでも続ける……。
……私は嘘つきだ、あるいはたぶん嘘つきだろう……。また、戦争をするというのは嘘つきだ、しかしそれは合法である。それはすなわち、人は大嘘をつく権利だけをもっているということなのか?……
……などなど……
もう何年も自伝を書いていない。第一、今引用したものだって多分贋物だ。だから、この瞬間に本当のことを言おうかと自問するのである。もしも私がなどなどなどなど しかし私は本当のこととは何かについて自問することを余儀なくされている。例えばもし私が年齢が四〇代であると言うとすると、それは本当のことだろうか? 実際私は、年をとればとるほど、自分が若いことを見いだすのだ。ほかに何が言えるだろうか? 私がいつも外に出ていったこととか? しかしそれは本当だろうか……。
教授たちと相容れなかったがためにパリ音楽院を出ていったとか、女性棟への夜間訪問のためにサナトリウムから追放されたとか、哲学上の意見の不一致から探求局から出ていったとか、政治的対立から国営放送から出ていったとか、制度上の不和からフランスにいなかったとか………。
しかしそれは本当に真実か?
またそれ以外に、私はさまざまな専門分化の波を乗り越え、いろいろな創作分野を試してみた(少々お堅い物言いを許してもらえば)。
音楽 器楽音楽の分野では:〈ソシエテ2〉ピアノ協奏曲とそしてもしピアノが女体だったら — 〈未完成交響曲〉 — 〈スイッチ〉 – 〈ソシエテ4〉 − 〈参加すべきか不参加であるべきか〉 − 〈ポンピドゥー家での諸大臣の踊り〉 — などなど……
電子音響音楽の分野では:〈切られた〉 — 〈異型接合体〉 — 〈音楽散歩〉 — 〈エレキピアノとテープのためのなどなど〉 — 〈声と2台のプリペアドテープデッキのためのモノロゴス〉 — 〈ほとんど何もないあるいは海岸の夜明け〉 — 〈あるアマチュアジャーナリストの日記〉 — などなど……
テクスト楽譜の方面では:〈私と同語反復するのはいかがですか?〉 — 間違った間違った大間違いをしちゃった — 〈自由よ、愛する自由よ〉 — 〈装置とその非装置〉 — 〈ポルノロゴス〉 — などなど……
国営放送のためのドキュメンタリー映画のジャンルでは(66年まで):大いなるリハーサル、ジェラール・パトリスと共作:メシアン、シュトックハウゼン、ヘルマン・シェルヘン、セシル・テイラー、マウリチオ・カーゲル。
独テレビのためのフィクションのジャンルでは:〈ソシエテ3あるいは少女たち〉(NDR) — 〈シェーンベルクを知っていますか?〉(WDR)
ラジオのジャンルでは:〈自画像の戯れ〉(SWR – バーデンバーデン)
演劇の方面では:〈もしもしこちら地球〉スライド、テープとオーケストラのためのプレイライトとタイムショー — (製作中)〈ほとんど何もないあるいは山中の夕陽〉 —
ただいまのところ以上である……。
【 参考文献表 】
バルトBarthes、ロランRoland『物語の構造分析』(花輪光訳)みすず書房、1979年。
ブーレーズBoulez、ピエールPierre『ブーレーズ音楽論 — 徒弟の覚書』(船山隆・笠羽映子共訳)晶文社、1982年。
ケージCage、ジョンJohn『サイレンス』(柿沼敏江訳)水声社、1996年。
コーCaux、ジャクリーヌJacqueline『リュック・フェラーリとほとんど何もない』(椎名亮輔訳)現代思潮新社、2006年。
Ferrari, Luc, parcours confus, Association Presque Rien autour de Luc Ferrari, Paris, 1999 - .
フェラーリFerrari、リュックLuc『センチメンタル・テールズ あるいは自伝としての芸術』(椎名亮輔訳)アルテス・パブリッシング、2016年。
ヤウスJauss、ハンス・ロベルトHans Robert『挑発としての文学史』(轡田収訳)岩波書店、1976年。
近藤譲『作品集「表面・奥行き・色彩」』CD、ALM Records (ALCD-93)。
河野健二『世界現代史19 フランス現代史』山川出版社、昭和52年。
クリステヴァKristeva、ジュリアJulia『記号の解体学 セメイオチケ1』(原田邦夫訳)せりか書房、1983年。
中本康夫・河合秀和・山口定『現代西ヨーロッパ政治史』有斐閣(有斐閣ブックス)1990年。
西村清和(編・監訳)『分析美学基本論文集』勁草書房、2015年。
Mâche, François-Bernard,Cent opus et leurs échos, Paris, L’Harmattan, 2012.
Mâche, François-Bernard, De la musique, des langues et des oiseaux, entretien avec Bruno Serrou, Paris, Éditions Michel de Maule / Institut national de l’audiovisuel, 2007.
椎名亮輔(編著)『音楽を考える人のための基本文献34』アルテス・パブリッシング、2017年。
Stoïanova, Ivanka, Geste-texte-musique, Paris, Union Générale d’Éditions (coll. 10/18), 1978.
Supplément au « Bulletin Socialiste » de juin 1972, in :
http://www.m-pep.org/IMG/pdf/Texte_Programme_commun_gauche.pdf(Le Programme commun de gouvernementの全文が読める。2018年7月31日アクセス)
渡邊啓貴『フランス現代史 — 英雄の時代から保革共存へ』中央公論社(中公新書)1998年。
(2018年8月3日執筆、9月4日改稿)